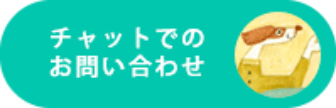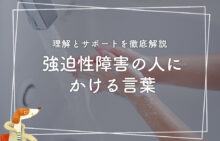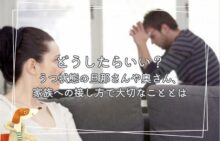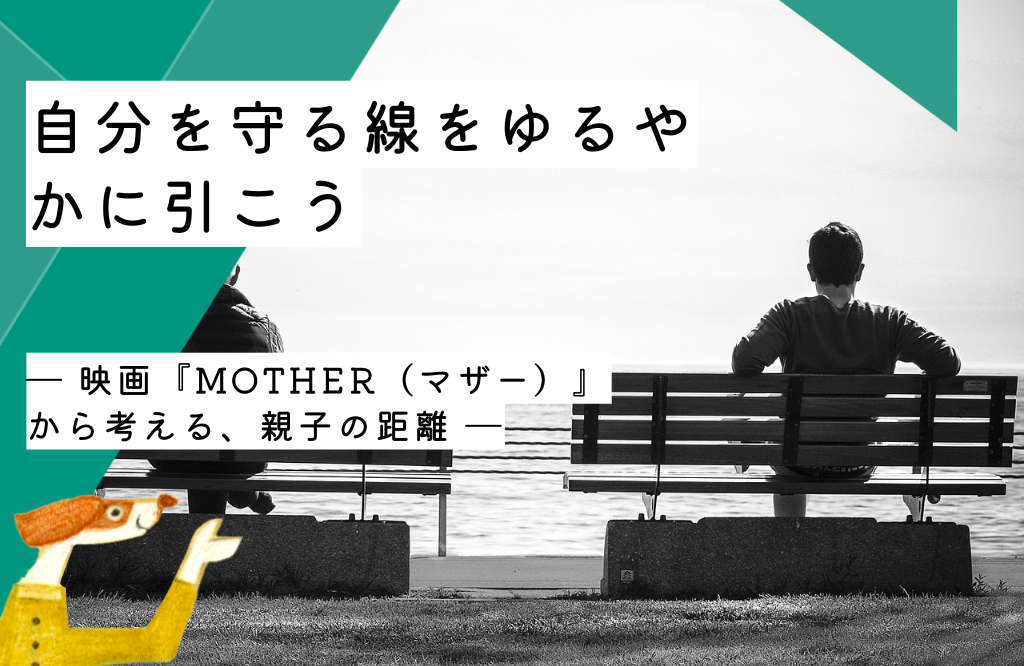
― 映画『MOTHER(マザー)』から考える、親子の距離 ―
人と関わることは、うれしくて、でも少ししんどいこともあります。
職場での人間関係、家族とのやりとり、友人との付き合い……どれも大切にしたいけれど、ふと「どこまで踏み込んでいいのかな」と迷う瞬間はありませんか?
近すぎると、息苦しくなる。
遠すぎると、さみしくなる。
その“ちょうどいい距離”を見つけるのは、実はとても繊細なことです。
心理学では、この心の距離を守るための「見えない線」のことを**バウンダリー(boundary)**と呼びます。
今回は、このバウンダリーをテーマに、毎日の中で自分を守りながら、やさしく人と関わる方法を考えていきます。
そして後半では、長澤まさみさん主演の映画『MOTHER(マザー)』を例に、親子という特別な関係の中で、この「線」がどう崩れていくのか、そしてなぜそれが誰にとっても起こり得ることなのかを見つめ直します。
目次
バウンダリーとは?――「ここから先は私の大切な領域」
バウンダリーという言葉は、ちょっと堅く聞こえるかもしれません。
でも意味はとてもシンプルです。
それは、**自分と他人の間にある“見えない線”**のこと。
線があることで、安心して関わることができます。線がなくなると、どちらかが無理をしたり、相手をコントロールしようとしたりして、関係が苦しくなってしまうのです。
たとえばこんな線があります。
- 心の線:相手の感情を自分の責任のように感じないこと。
- 体の線:無理なスキンシップや夜中の呼び出しを断る勇気を持つこと。
- 時間の線:仕事と休息の区切りをしっかりつけること。
- 頼まれごとの線:できないことを「今は難しい」と伝えること。
- 考えの線:意見が違っても、相手を否定せず、自分の価値観を守ること。
こうした線を意識することで、自分を大切にしながらも、人と穏やかに関わることができます。
バウンダリーは、「冷たさの線」ではなく、「お互いを守るためのやさしい線」なのです。
誰にとっても、バウンダリーを保つのはむずかしい
私たちは、「断ったら嫌われるかも」「申し訳ない」と感じる生きものです。
だから、つい自分を後回しにして、相手に合わせすぎてしまうことがあります。
けれど、バウンダリーを守ることは“わがまま”ではなく、自分も相手も尊重すること。
線を引くことで、関係を壊すのではなく、長く続けられる関係に整えていくのです。
とはいえ、それが難しいのも事実。
たとえばこんな経験はありませんか?
- 断れずに、気づいたら予定がいっぱい。
- 相手の気分にふり回されて、自分の調子が崩れる。
- 「家族だから」「親だから」「子どもだから」と言い聞かせて、我慢を続けてしまう。
そんなときは、自分の中の線が少し薄くなっているサインかもしれません。
その線をゆるやかに引き直すことから、関係はまた整い始めます。
線があいまいになりやすい場面
バウンダリーは、近しい関係ほど崩れやすいものです。
「信頼している相手だからこそ」「助けてあげたいから」と思うほど、気づかないうちに線を越えてしまうことがあります。
- 家族との関係
「あなたのためを思って」と言いながら、相手の選択を奪ってしまう。
逆に、家族の感情をすべて自分が背負ってしまう。 - 職場での関係
「頼まれたら断れない」「自分がやらなきゃ」と思って、時間も心もすり減らす。 - 友人・SNSでの関係
「すぐ返信しなきゃ」「既読をつけたら返さなきゃ」と焦ってしまう。
もし、「休んでも疲れが取れない」「罪悪感で行動してしまう」「自分の時間がなくなっている」
そんな状態が続いていたら、それは線が曖昧になっているサインかもしれません。
線を守るための小さなコツ
バウンダリーを保つには、「強く言う」ことよりも、「やさしく、でもハッキリ伝える」ことが大切です。
- 短く断る:「今回は難しいです」「今はできません」
→ 理由を長く言わなくても大丈夫。誠実に伝えれば、十分に伝わります。 - 時間のルールを決める:「連絡は夜9時まで」「相談は15分」など。
→ 先に“枠”を作ることで、無理を減らせます。 - “私”を主語にする:「あなたが悪い」ではなく、「私は今、休む時間が必要です」。
→ 相手を責めずに、自分の気持ちを伝えるだけで、関係は柔らかくなります。 - 合図を決めておく:家族や同僚と「ここで休憩」のサインを共有する。
→ 感情的になりすぎる前に、一呼吸おける。 - 保留を使う:「すぐには決められません」「明日返事します」。
→ その場の勢いに流されずに、冷静に考える時間を持てます。 - 助けを借りる:相談できる人や機関を持つ。
→ 「自分でなんとかしなきゃ」と抱えすぎないことも、立派な線引きです。
線は、一度引いたら終わりではなく、そのときどきで調整していいものです。
少しずつ、柔らかく、自分のペースで整えていきましょう。
映画『MOTHER(マザー)』が教えてくれる、親子の境界線
映画『MOTHER(マザー)』(2020年/監督:大森立嗣・主演:長澤まさみ)は、
「親と子の境界線がなくなったとき、人はどこまで壊れてしまうのか」という問いを突きつけてくる作品です。
物語の中心にいるのは、母・秋子と息子・周平。
母は、社会から孤立しながらも、自分の世界を維持するために、息子を支えではなく“道具”のように扱ってしまいます。
そして周平は、「母を守らなければ」「母を悲しませたくない」という思いで、徐々に自分の人生を母に明け渡していきます。
この関係は、映画だから特別なのではなく、私たちの日常の中にも小さく存在しています。
たとえば、「親が喜ぶ顔が見たい」「家族のためにがんばらなきゃ」と思う気持ちは誰にでもあります。
でも、それが行きすぎると、「自分の気持ちよりも相手を優先することが当たり前」になり、線がぼやけてしまうのです。
母親が“唯一の世界”になってしまうと
劇中では、秋子が息子・周平に対して「あなたしかいない」「あんたがいなきゃ生きていけない」と繰り返します。
その言葉は一見、愛情のようにも聞こえます。
しかし、そこには「あなたの世界は私の中にしかない」という支配が隠れています。
周平は母を助けたい一心で、学校にも行けなくなり、外の世界とのつながりを失っていきます。
母の機嫌や期待に合わせて生きるうちに、彼の「自分の意思で選ぶ」という線が消えていくのです。
私たちもふと、「あの人がいなければ自分はどうなってしまうんだろう」と感じることがあります。
それは、人を大切に思う気持ちの裏にある、境界線の揺らぎかもしれません。
子どもが“親の役割”を背負ってしまう
映画の中で、周平は次第に“母を支える存在”として扱われます。
母親が生活の軸を失い、頼る相手を息子一人に絞ってしまうため、子どもが“親のような立場”を担うようになるのです。
食事や金銭のやりとり、生活の段取り。
それらを本来の年齢では背負えない形で引き受け、やがて「自分が母を支えなければ生きていけない」と信じ込んでしまう。
この関係は、実はとても身近な問題でもあります。
親が弱ったとき、子どもが無意識に「自分がなんとかしなきゃ」と感じる瞬間は誰にでもある。
それ自体は自然な反応ですが、その状態が長く続くと、心の中に「子どもとしての線」がなくなってしまうのです。
世界が“家族だけ”になる怖さ
映画では、母と息子が社会からどんどん孤立していきます。
親戚や学校、支援機関とのつながりは途切れ、二人だけの世界に閉じこもっていく。
その空間は、愛情と依存が混ざり合い、外の世界が敵のように見える場所になっていきます。
この描写は決して他人事ではありません。
たとえば、家族の問題を「外には言えない」と抱え込むこと。
「家庭のことだから」と周囲が距離を置くこと。
その積み重ねが、親子を外の世界から孤立させてしまうのです。
どんなに小さな悩みでも、「誰かに話せる」という線が一本あるだけで、人は壊れずに済むことがあります。
家族の中に閉じこもらないこと。
それもまた、バウンダリーを保つ大切な要素です。
「母さんが好きなんです」――愛と境界のあいだに
映画の終盤、周平が放つ「母さんが好きなんです」という言葉は、聞く人の胸を締めつけます。
それは純粋な愛情のようでいて、同時に「この人以外に自分の世界がない」という叫びにも聞こえます。
愛することと、相手の人生を自分の中心に置くことは、似ているようで違います。
どちらも優しさから生まれる行動だけれど、境界線を越えてしまうと、愛は“支配”にも“依存”にも変わってしまう。
親子の関係で最も難しいのは、この「愛」と「境界」のバランスです。
子どもを心から愛しながらも、「あなたはあなたの人生を生きていい」と伝えられるか。
そして、親自身も「私の幸せは、子ども以外にもある」と信じられるか。
映画『MOTHER』は、そのどちらも難しいことを、静かに、そして痛いほどリアルに映し出しています。
親子のバウンダリーを守るということ
この映画が教えてくれるのは、「親子だからこそ線が必要だ」ということです。
線があるから、互いに呼吸ができる。
線があるから、相手を本当の意味で尊重できる。
親は、子どもが自分の力で歩けるように、見守りながら線を引く。
子どもは、親の人生を背負わず、自分の足で進む線を見つける。
そして、親子の世界だけでなく、外の大人や友人、地域や支援機関とつながること。
その“外との線”を持つことで、親子の関係はより健全に保たれます。
『MOTHER』のような極端な崩れは、実は小さな日常の積み重ねの先にあります。
だからこそ、いま、自分の家族との関係を少しだけ見つめ直してみる。
それが、バウンダリーを整える最初の一歩になるのかもしれません。
「線を引く」のは練習が必要
バウンダリーを整えるのは、特別な人だけの力ではありません。
少しずつ練習すれば、誰でもできるようになります。
① 私の線引きメモ
ノートに「心・体・時間・頼まれごと・考え」と書いて、それぞれに「守りたいこと」を1つずつ書いてみましょう。
(例:「夜はスマホを見ない」「疲れたときは断ってOK」など)
② ひとこと練習
「今は返事できません」「今日はここまでにします」「その案は今回は見送ります」——
声に出して練習すると、いざというとき自然に言えます。
③ 24時間チャレンジ
今日、ひとつだけ“NO”を言ってみる。
そして、できたら「よくできたね」と自分をほめる。
たったそれだけで、自分の中の線が少し太くなります。
よくある悩みとヒント
Q:断ると冷たい人に見えない?
→ 断ることは、相手を思いやることでもあります。
無理に引き受けて疲れてしまうより、誠実に「今は難しい」と伝えた方が、長い目で見れば関係が良くなります。
Q:家族には言いづらい…
→ ルールを「一緒に決める」のがおすすめです。
「夜9時以降は休む」「話が長くなったら合図で休憩」など、前もって決めておくことで衝突を防げます。
Q:子どもの線はどう守ればいい?
→ 大人がまず「線を見せる」ことが大切です。
断ってもいい、助けを求めてもいいという姿を見せることで、子どもも安心して「NO」や「SOS」が言えるようになります。
線を引くことは、やさしさのひとつ
バウンダリーは、誰かを遠ざける線ではありません。
むしろ、お互いが安心して近づけるための線です。
「線を引く=冷たい」ではなく、「線を引く=思いやり」。
それは、自分を守ると同時に、相手の領域を尊重する行為です。
うまくできない日があっても、気にしなくて大丈夫です。
「今日はどんな線を守れたかな?」
そう自分に問いかけるだけで、線は少しずつ整っていきます。
線を引くことは、自分を大切にすること。
そして、自分を大切にできる人は、他の人にもやさしくなれます。

 Blog
Blog