
周囲/当事者の方へ
うつを患う一人暮らしの友人をサポートする場合に心がけたいこと
 To supportersまわりの方へ
To supportersまわりの方へ
友人がうつ病など心の病になったとき、一体何ができるでしょうか。どうにか力になりたいと思っていても、どうしていいか分からないという方は多いでしょう。
心の病になると、「誰も自分のことを分かってくれない」「自分は一人だ」と孤独を感じることもあります。そんなとき、日頃から良好な関係を築いている友人は心の支えとなるでしょう。
友人は家族のように日常生活をともにするわけではないため、家族よりも物理的な距離があり、お互いにとって居心地のいい関係をつくりやすいといえます。それでは実際にどんなことを心がけて接していくといいのでしょうか。
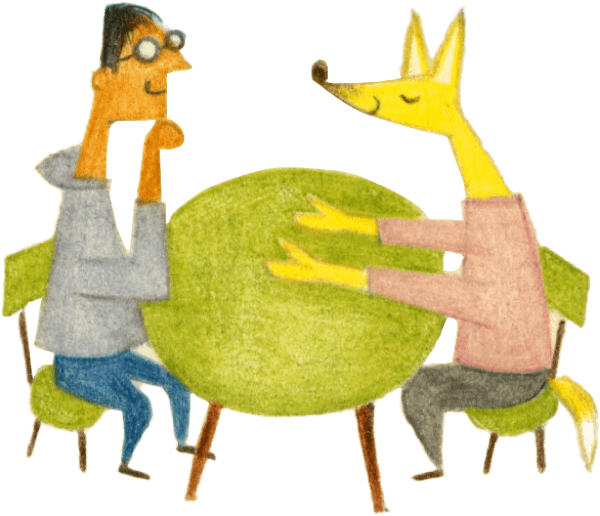
友人として具体的にどのような接し方をするといいのでしょうか。当事者と友人、双方の負担にならず、これまで通りよい友人関係を続けるためのポイントをご紹介します。
友人を支えるために必要なことは、基本的には普通の人間関係と変わりません。病気になったからといって態度を変えると、当事者は「腫物扱いされた」と感じてしまいます。病気になっても別人になるわけではありません。病というフィルターを通さず、以前と同じように話ができる友人がいれば、それだけで救われることもあります。
心の病のことを周囲に開示したくないという方は多く、実際全ての友人に開示するということはほとんどありません。また、話すまでには時間がかかるケースもあります。仮に調子が悪そうな友人がいても、心の病と決めつけたり疑ったりするのではなく、体調を心配していることをまずは伝えてみましょう。
症状の波(増減の幅)は本人にとってもつかみにくく、特に症状が重くなる急性期は気のもちようではどうにもなりません。「楽しみたくても楽しめない」時期が存在するという、うつ症状の性質を理解し、約束をするときにはドタキャンしてもいいことを伝え、その前提で予定を組むといいでしょう。
症状が重い急性期は、連絡をすることが負担になることもあるため、本人からの連絡を待つくらいがいいでしょう。ある程度回復して話せるようになってきたら、ちょうどいい連絡頻度を率直に話し合ってみましょう。また、症状が安定しない時期は直接会ったり、電話をするより、メールやチャットでの連絡のほうが、負担が少ない場合もあります。
友人側の心構えとして大切なのは、無理をしないことです。「病気を理解すること」と「病気だから何でも許すこと」は同じではありません。症状だからしょうがないと我慢ばかりしているとストレスが溜まりますし、当事者側にも罪悪感が募っていきます。お互いに適切な距離をとって、対等な関係を意識するといいでしょう。
友人としてうつ病など心の病に対応するには、理解と支援が鍵です。詳細については、「うつを患う一人暮らしの友人をサポートする場合に心がけたいこと」というブログ記事で、友人をサポートするための具体的な方法を紹介しています。
