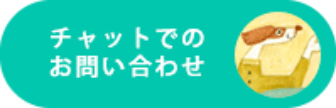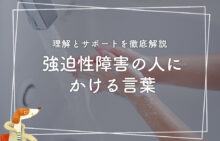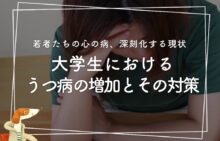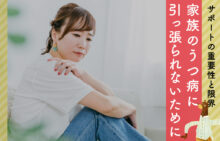〜知られざる“男性産後うつ”とその乗り越え方〜
「子どもが生まれたら、幸せいっぱいの毎日が待っていると思っていた——」
でも実際には、戸惑い、不安、苛立ち…そしてふと感じる“自分の不調”。
これは、男性にも起こる「産後うつ」かもしれません。
今回は、公認心理師の視点から、男性の産後うつの実情や背景、そして社会復帰に向けたサポートのあり方についてお話しします。
男性の産後うつとは?
「『自分には関係ない』と思っていませんか? 〜男性にも起こる産後うつ〜」
産後うつと聞くと、まず思い浮かべるのは母親かもしれません。しかし、実は父親もまた産後うつを経験することがあります。これは決して珍しいことではなく、実際に国内外の研究では、およそ10人に1人の父親が産後うつの症状を経験するというデータもあります。
父親の産後うつは、子育てや生活の変化に適応する中で、プレッシャーや孤独感、無力感を感じやすくなることから発症します。とくに「父親だから」「男だから」という固定観念が強いと、「つらい」と言えないまま心身のバランスを崩してしまうことも少なくありません。
男性の産後うつで起こる症状と諸問題
「怒りっぽくなったり、やる気が出なかったり…これってうつ?」
男性の産後うつでは、女性と異なり「イライラしやすい」「怒りっぽくなる」「無気力」「仕事への集中力の低下」などの症状が目立つ傾向があります。以下は代表的な症状です:
- 楽しかったことが楽しめない
- 気分の落ち込みや焦燥感
- 睡眠の乱れ(寝つきが悪い、早朝覚醒など)
- 食欲の変化(過食や拒食)
- 子どもとの関わりを避ける
- パートナーへの攻撃的な態度や口論の増加
これにより、家庭内の雰囲気が悪化したり、仕事に集中できずパフォーマンスが低下したりすることもあります。最悪の場合は離職や家庭の崩壊につながることもあるため、早期の気づきと対応がとても重要です。
男性産後うつの原因・背景
「“父親”という新しい役割と、その重圧」
男性が産後うつになる背景には、複合的な要因があります。代表的なものは以下のとおりです:
- 役割の変化:急に「父親」という役割を求められ、何が正解か分からず戸惑う。
- 睡眠不足・生活リズムの乱れ:夜泣きなどによる慢性的な疲労。
- パートナーとの関係変化:子育て中心の生活により、夫婦間のコミュニケーションが不足する。
- 経済的・社会的なプレッシャー:家計を支える責任が重くのしかかる。
- 相談できる相手がいない孤立感:周囲に同じような悩みを話せる人がいない。
特に、「弱音を吐くこと=甘え」と捉えがちな文化的背景がある日本では、男性が自分の不調に気づきにくく、誰にも相談できず悪化させてしまうケースも目立ちます。
男性の産後うつに対しての相談先
「ひとりで抱え込まないで。あなたのための“相談できる場所”」
男性の産後うつは「一人で抱え込まないこと」が何よりも大切です。以下のような相談先があります:
・心療内科・精神科
まずはメンタルの専門医に相談することが基本です。診断や必要な治療、薬物療法などを受けることができます。
・自治体の子育て支援窓口
各市町村には、子育て支援の一環として父親の相談も受け付けている窓口があります。無料で利用できる場合も多く、初めての相談先としてもおすすめです。
【最後に】心が疲れたとき、立ち止まってもいい
父親である前に「一人の人間」として、心の健康は何より大切です。前述した症状が続ているのであれば、それは 産後うつのサインかもしれません。「こんなことで相談してもいいのかな」と思う前に、まずは話してみてください。

 Blog
Blog